この曲のコンセプトについてです。
4曲目「Trick nor Treat」を投稿しました。 YouTube https://youtu.be/iP2CavdB5eA?si=We3XTJ-A2XrL6Clo ニコニコ動画 【初音ミク】Trick […]
ハロウィンとは本来どんな祭り?
ハロウィンはもともと、古代ケルト人が行っていた「サウィン祭」というお祭りが起源だそうです。
これは秋の収穫を祝い、同時に亡くなった人の魂を迎えるための行事でした。
つまり、ハロウィンは「豊穣の祝い」と「死者と生者が交わる日」だったんですね。
日本でいうお盆と正月的な感じ?
収穫と死者を迎えるためのケルト文化の祭り
古代ケルトでは10月31日が一年の終わりで、この夜に「死者の魂が家族のもとに帰ってくる」と信じられていたそうです。
そのため、人々は悪霊に憑かれないように仮面をかぶったり、焚き火を焚いたりして身を守っていたらしい。
つまり、今の“仮装”のルーツは「悪霊を怖がらせるための防御」だったというわけです。
ほえ〜
なぜカボチャ?ジャック・オー・ランタンの物語
では、なぜハロウィンといえばカボチャなのでしょうか。
それは「ジャック・オー・ランタン」という、アイルランドの伝承がもとになっています。
「悪魔をだまして地獄にも天国にも行けなくなった男・ジャックが、カブをくり抜いて灯りをともした」
その話がアメリカに渡ったとき、より手に入りやすいカボチャに変わったそうです。
つまり、ハロウィンの「カボチャの灯り」には、”死者を導き、悪霊を遠ざける”という意味が込められていたんですね。
なるほど〜
知らんがな
だから何やねん
・・・って感じの人がほとんどでしょう。
時代は移ろい、ハロウィンはコスプレ仮装パーティー的な祭りに変わりましたよね。
非日常感を楽しむ口実のようなものになり、本来の目的や風習はもう形だけになってしまいました。
そもそも、なぜカボチャなんだろう?と考えたり調べたりする人自体が少数派なのでは?
目的は移ろうものである
どんな祭りも、時代を経て目的も形も変わっていくものです。
地元の祭りも、もはやお酒を飲んで盛り上がることが目的であり、本来の意味などは重要視されていないでしょう。
ハロウィンもその一つです。
もともとは“死者を迎える日”だったのに、今では“コスプレワイワイパーリナイ”になりました。
そういうもんですよ。
やってる間に本来の目的を見失うことは多々あります。良くも悪くも。
「Trick or Treat(お菓子をくれなきゃイタズラするぞ)」という言葉も、もはや単なる合言葉になっていますよね。
まぁある意味で「仮面を被った言葉」「騙し合い」「甘い誘惑」という文脈において、トリックもトリートも、ハロウィンの中には概念的に残っているのでしょう。
『Trick nor Treat』
そんな曲です。
待ちわびたようにカボチャの目が光る
昨日より明るいオレンジ色の夜
忘れ去られて奪われたカブ
捨てられた種から咲く宵の花
輝く月が始まりを告げる
風に習う事なく騒ぎたいだけ
Trick nor Treat!
もう何も必要じゃないの
合言葉なんて別にどうでも良いから
Trick nor Treat!
今はただ踊りたいだけよ
お菓子もイタズラも魔法の邪魔はしないで
幻想の夜に騙されたいだけ
仮面の下には素顔はないわ
月の明かりで作られた虹と
もう思い出せない声の温もり
彷徨い歩く影の無い形
人混みに紛れて笑う思惑
Trick and Treat!
欲に塗れた夜の帷
目的や始まりは別にどうでも良いから
Trick and Treat!
嘘に塗れたオレンジ色
お菓子もイタズラもきっかけにすぎないわ
Trick or Treat?
独り歩きの合言葉
目的や始まりは誰も興味は無いから
Trick or Treat?
今はただ騒ぎたいだけよ
お菓子もイタズラも魔法の呪文になるから
さいごに
改めて歌詞を見ると皮肉っぽいですかね?
ハロウィンはホラーなのにどこか明るい雰囲気として印象深いです。
ハロウィン以外の催しや祭りについても、本来の意味や由来、発案の経緯などを調べてみるのも面白いですね。
おおよそ豊穣や大漁祈願、または手向けや供養なのでしょう。
これから先、日本において新たな祭りが文化として根付く事はあるのでしょうか?
そして、果たしてそれがポジティブなものか、ネガティブなものか。
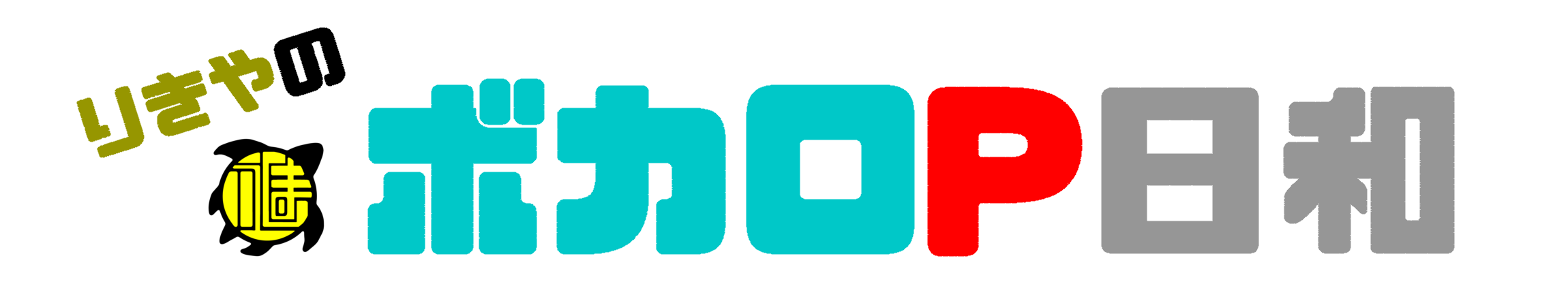













コメントを書く